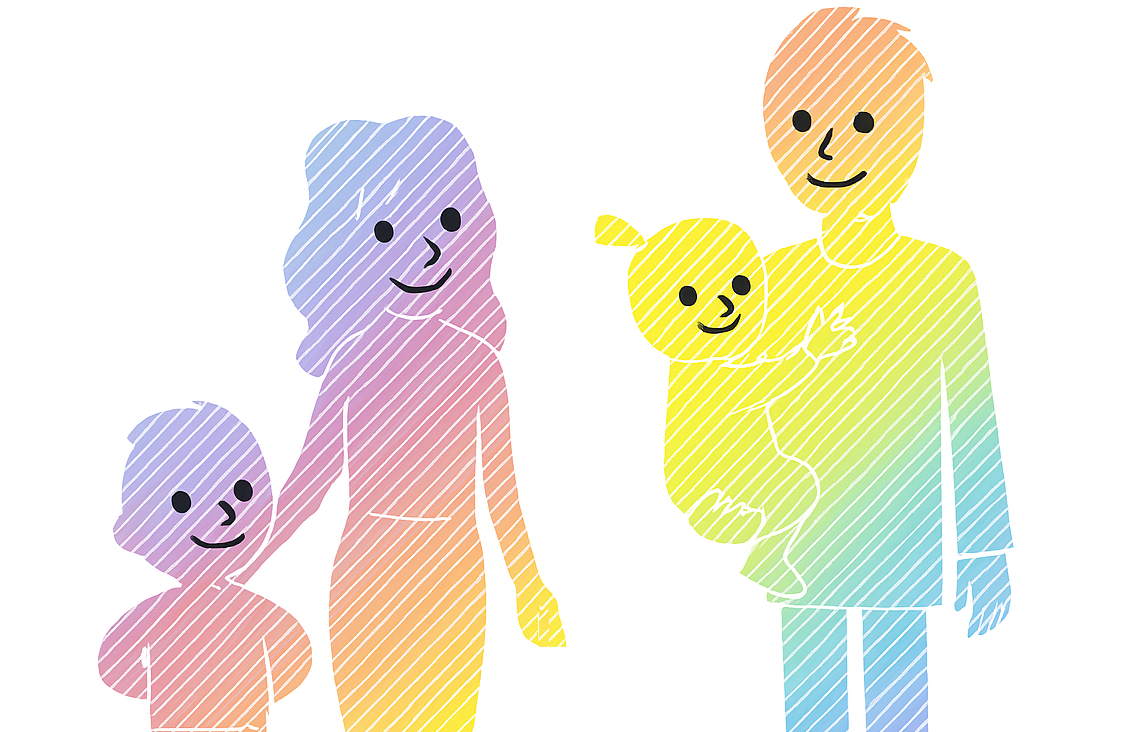
「療育や特別支援を勧められたら?」前編:ショックと拒絶の背景にあるもの
2025年10月12日 17:15
療育や特別支援を勧められたらどうすればよい?
前編:ショックと拒絶の背景にあるもの
「うちの子は普通です/障害者扱いしないでください!」

そんな言葉を、保育士や先生に思わずぶつけてしまったことはありませんか?
あるいは、心の中でそう叫びながら、何も言わずにその話題を避け、そんな話などなかったかのようにスルーしてしまったことがあるかもしれません。
療育や特別支援という言葉は、多くの保護者にとって「わが子が普通ではない」と突きつけられるような衝撃を伴います。それは、親としての自信や希望、そして子どもへの愛情が否定されたように感じる瞬間でもあります。
でも、少しだけ冷静になってみましょう。
先生たちが伝えようとしていることは、本当に「障害者扱い」なのでしょうか?
今回は、療育や特別支援を勧められたときに起こる保護者のショックや拒絶の背景を、保護者目線で丁寧にひもといてみたいと思います。
家庭と学校で見える「子どもの姿」は違う
家庭では、子どもが困る前に親や兄弟が気づいてフォローすることができます。
例えば、言葉に詰まってしまったとき、親が代弁してくれる。
集中力が切れそうなとき、兄弟が遊びに誘って気分転換してくれる。
そうした“ミニマムな社会”の中では、子どもは安心して過ごしやすいし、感情を爆発させる前に気をそらしやすいでしょう。
しかし、保育園・幼稚園や小学校は違います。
保育園や幼稚園では「25人の中の1人(年長クラス)」、小学校では「35人の中の1人」、として過ごします。
先生は一人ひとりの様子を気にかけながらも、全体の流れを止めずに授業や活動を進めなければなりません。
そんな中で、
・授業中や一斉指示中に立ち歩いてしまう
・ちょっかいを出してしまう
・不規則発言が止まらない
・読む力や書く力に極端な偏りがある
といった行動が目立つようになる。と、保育園や幼稚園の保育士や先生は
「このまま進学したら、45分間授業に座って話を聞いていられるだろうか?」
「友達から仲間外れにされたりしないだろうか?」と心配する。
小学校の担任は
「普通のクラス(通常学級)で、みんなと同じように勉強をして、学力が身につくものだろうか」
「気持ちの切り替えとか、クラスのルールやマナーを守れる力などを身につけないと、社会で自立できないのでは」
と心配する。
それは、家庭では見えない、あるいは見えにくい問題なのです。
「偏見では?」と感じたときに立ち止まってみる
保護者が「うちの子を障害者扱いしないで」と感じるのは、当然のことです。誰だって、わが子を否定されたような気持ちになります。
それでも、ここで一度立ち止まって考えてみてほしいのです。
保育士や先生は、子どもを「障害者」としてラベリングしたいわけではありません。むしろ、「このままでは本人が困る場面が増えてしまうかもしれない」と心配しているのです。
実際、支援を受けずに過ごしていると、
・授業についていけずに学力が伸びない
・友達との関係がうまくいかず孤立する
・注意されることが増えて自己肯定感が下がる
といった“二次的な困難”が積み重なる危険が高まります。
そして、成長するにつれて、
・教室からエスケープする
・暴言や暴力
・不登校
などの深刻な問題行動に発展することもあります。
「偏見だ」と思って支援を拒んでしまうことで、結果的に子どもがもっと苦しむことになるかもしれないのです。
担任は本当に「バカにしている」のか?
「うちの子をバカにしているのでは?」
「決めつけているだけでは?」
そんな疑念が湧いたときは、ぜひ情報を集めてみてください。
・連絡帳に書かれている内容
・面談での先生の言葉や表情
・学校での観察記録や支援会議のメモ
・他の保護者の話や、子ども自身の言葉
それらを冷静に見てみると、先生が「困っている子どもを何とかしたい」と思っていることが伝わってくるかもしれません。
もちろん、伝え方が不十分だったり、言葉選びが適切でなかったりすることもあります。でも、そこに悪意があるとは限りません。
むしろ、先生自身も「どう伝えれば保護者にわかってもらえるか」と悩んでいることが多いのです。
支援を拒むことで起こる“手遅れ”のリスク
支援を受けることは、決して「障害者になること」ではありません。
それは、子どもが自分らしく、安心して学び、成長していくための“環境づくり”なのです。
療育や特別支援は、
・子どもの得意・不得意を分析する
・日常生活の中で困っている場面を見つける
・必要なスキルを練習する
といったプロセスを通して、子ども自身の力を引き出していきます。それを拒んでしまうと、
・支援のタイミングを逃す
・困りごとが深刻化する
・周囲との関係が悪化する
といった“手遅れ”のリスクが高まってしまいます。
最後に:気になる行動や発言を変えるには…
もし、先生から療育や特別支援を勧められたら、まずは「なぜそのように感じたのか?」を聞いてみてください。
そして、家庭では見えない子どもの姿に目を向ける意識をもってみてください。
気になる行動や発言を変えるには、
・検査で得意・不得意を分析する
・教育相談で日常生活を見直す
・通級で必要なスキルを練習する
といった支援が役立ちます。
本相談室では、そうした支援の第一歩をお手伝いしています。
「うちの子、ちょっと気になるかも…」と思ったら、ぜひ一度ご相談ください。
保護者の不安に寄り添いながら、子どもに合った支援を一緒に考えていきます。