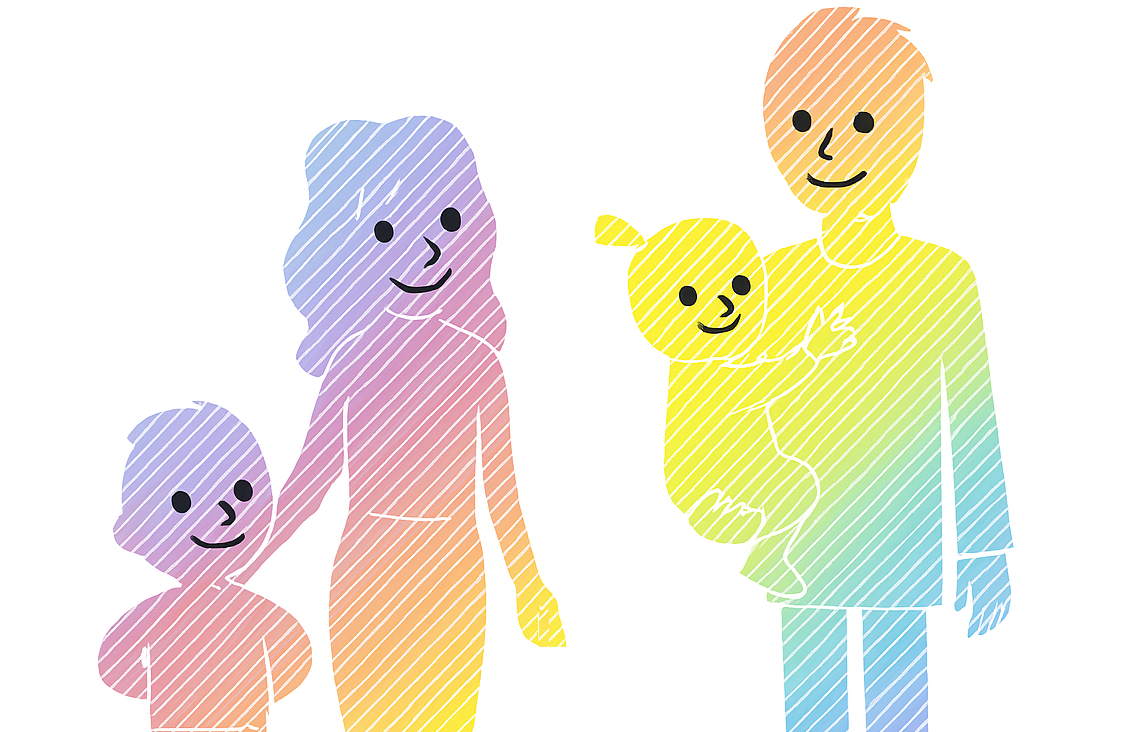
「療育や特別支援を勧められたら?」 後編:冷静に向き合うためのヒントと選択肢
2025年10月12日 17:18
療育や特別支援を勧められたらどうすればよい?
後編:冷静に向き合うためのヒントと選択肢
前編では、療育や特別支援を勧められた際に保護者が感じるショックや拒絶の背景についてお話ししました。
今回はその続きとして、「どう受け止めればよいのか」「落ち着いて話し合うことはできるのか」という視点から、冷静に状況を整理し、子どもに本当に必要な支援を見極めるヒントをお届けします。
「本当にうちの子に支援が必要なの?」という疑問
保育士や担任の先生から「療育や特別支援教室を検討してみては?」と提案されたとき、
「うちの子にそんな必要はない」「ちょっと落ち着きがないだけでは?」と感じる保護者は少なくありません。
家庭では問題が見えにくいことがあるからです。しかし、保育園や学校という集団の中では、以下のような困りごとが表面化しやすくなります。
指示が通りにくい
活動の切り替えが苦手
友達との距離感がつかめない
課題に取りかかるまでに時間がかかる
この違いはなぜ生じるのか。ぜひ客観的に考えてみてください。
支援の必要性は、保護者や支援者の都合ではなく、子ども自身が「困っているかどうか」で判断されます。
本人が言葉にできない困り感は、周囲の観察と分析によって初めて見えてくるものです。
特に集団生活の中では、家庭では見えなかった一面が現れることがあります。
「黙らせてしまう」子育てが困り感を隠してしまうことも
子どもは基本的に保護者のことが好きです。
そのため、親の前ではわがままを抑えようと努力します。
好きではなかったとしても、成人するまで生活するために自然と自分を押さえ、遠慮するようになります。
「うちは我がまま放題ですよ」と感じる方もいるかもしれません。
その場合でも、「黙れ!」「ちょろちょろするな」といった叱責で行動を抑えていることはありませんか?
これでうまくいく間は、保護者は「ちょっとやんちゃだけど、私(俺)が叱れば言うことを聞くから問題ない」と思うようになるでしょう。
保育園や学校からの指摘に納得できないのも当然です。
困り感が表に出ないように仕向けている状態では、支援の必要性が見えにくくなってしまいます。
 「先生はうちの子をバカにしているのでは?」という不安
「先生はうちの子をバカにしているのでは?」という不安
「先生がうちの子を低く見ているのでは?」と感じる保護者もいます。
しかし、多くの先生は「この子の力をもっと引き出したい」と思って支援を提案しています。
伝え方が不十分だったり、言葉選びが適切でなかったりすることもありますが、
そこに悪意があるとは限りません。
むしろ、先生自身も「どう伝えれば保護者に理解してもらえるか」と悩んでいることが多いのです。
まずは冷静に、「なぜそのような提案があったのか?」を聞いてみましょう。
以下のような具体的なエピソードを確認することで、保育士や先生の意図が見えてくることがあります。
授業中の様子
友達との関わり方
課題への取り組み方
情報収集のすすめ:学校での様子を知るために
家庭と学校では、子どもの見え方が異なります。
だからこそ、保護者が学校での様子を知るための情報収集が重要です。
おすすめの方法は以下の通りです:
連絡帳や日々の記録を読み返す
→ どんな場面で困っているのか、先生がどう対応しているのかがわかります。
読んでいてつらいと感じる場合は、小説やコラムを読むような感覚で、第三者の立場で客観的に受け止めてみましょう。面談で具体的な事例を聞く
→ 抽象的な「落ち着きがない」ではなく、「○○の時間に○○をしてしまう」などの具体例を確認。
たとえば、着替えができない場合は、家庭で体操着や水着を着てみる。
お風呂でプールごっこをしたり、公園で体操着を着て遊んだりして、楽しい記憶をつくることで前向きになれるかもしれません。子ども自身に聞いてみる
→ 「どうしてこんなことしちゃったの?」「何に困っている?」と優しく聞いてみましょう。
たとえ答えが予想外でも、怒らずに「どうすれば減らせるか」を一緒に考えることで、
子どもが安心して相談できるようになり、家族での対話が問題解決につながっていきます。
支援を受けることは“特別”ではない
「通級」や「療育」と聞くと、「特別な子が行く場所」というイメージを持つ方もいます。
でも、それは誤解です。
支援とは、「その子がその場で安心して過ごすための環境調整」です。
たとえば、
音読が苦手な子に視覚的な補助をつける
切り替えが苦手な子にタイマーやスケジュールアプリを使う
距離感がわからない子にロールプレイで練習する
こうした工夫はすべて“支援”です。
支援を拒むことで、以下のようなリスクが高まります:
本人が困り続ける
周囲との関係が悪化する
自己肯定感が下がる
支援は、子どもが「自分らしく」過ごすための手段です。
それを受けることは、決して恥ずかしいことではありません。
習い事感覚で始められる支援もある
「通級って手続きが面倒そう…」
「診断書や受給者証が必要なのでは?」
そんな声もよく聞きます。
確かに、自治体の制度を使った支援には書類や審査が必要な場合があります。
しかし、もっと気軽に始められる支援もあります。
たとえば、私たちの多摩湖畔通級支援室では、診断書も意見書も受給者証も不要。
必要な時に、必要な回数だけ。
習い事感覚で、療育的な通級支援を受けることができます。
「ちょっと気になる行動がある」
「学校で指摘されたけど、どうすればいいかわからない」
そんなときに、まず一歩を踏み出せる場所です。
なお、より適切な支援を行うために、これまでにWISC検査を受けたことがある場合は、その結果をご持参ください。
受けたことがない場合は、WISC基本コースの受診が必要となります。
検査結果は、子どもの得意・不得意を客観的に把握するための大切な資料です。
それをもとに、支援の方向性を一緒に考えていきましょう。
最後に
療育や特別支援を勧められたとき、保護者として戸惑うのは当然のことです。
突然の提案に驚き、否定されたような気持ちになる方もいるでしょう。
しかし、その背景には「この子が困っているかもしれない」という先生の気づきがあります。
その気づきを拒むのではなく、まずは「本当に困っているのか?」を一緒に考えてみること。
そして、必要な支援を受けることで、子どもが安心して過ごせる環境を整えていくこと。
それが、保護者としてできる最も大切なサポートなのかもしれません。