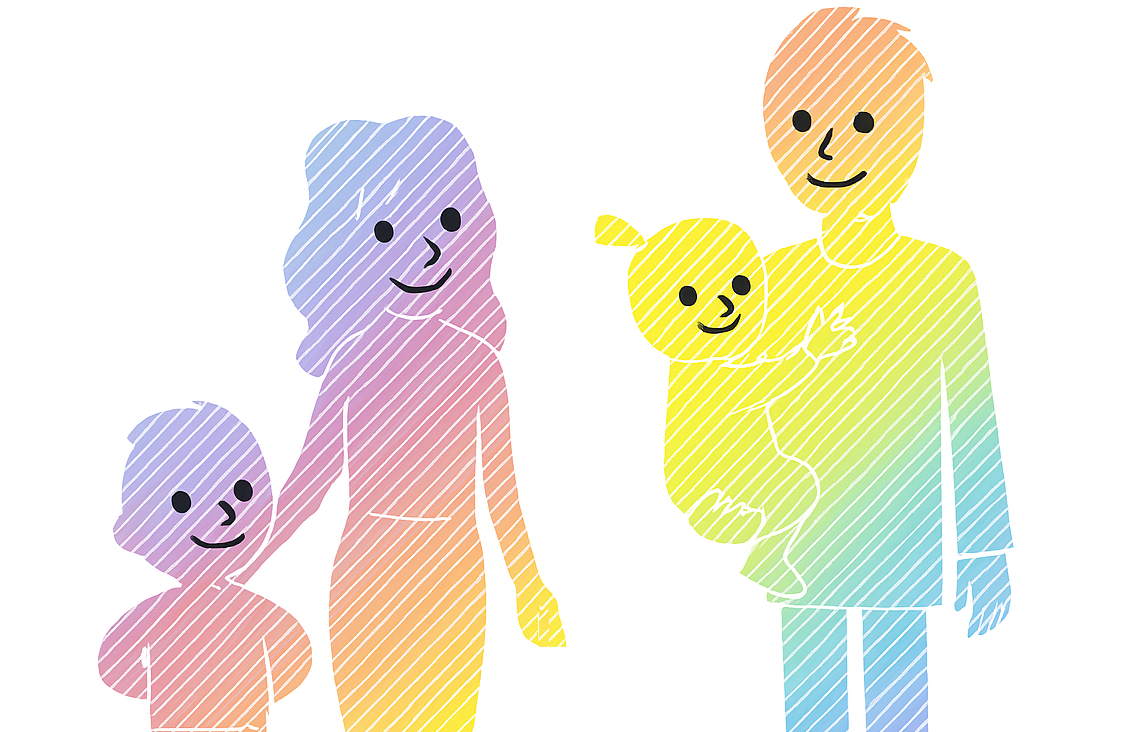
なぜ小学生にも療育が必要なのか?
2025年10月12日 17:25
なぜ小学生にも療育が必要なのか?
小学生だからこそ、療育が必要な理由
「療育」と聞くと、児童発達支援センターや医療機関などで行われる、未就学児を対象とした支援を思い浮かべる方が多いかもしれません。確かに、療育は保育園や幼稚園の年齢で受けやすく、作業療法士による感覚統合や言語聴覚士による言語療法などの専門的な支援を受けられる環境も整ってきています。
しかし、小学生になった途端に、療育の選択肢はぐっと少なくなります。困りごとが続いているにもかかわらず、「もう学校に通っているから」「学習が中心になるから」といった理由で、支援の機会が失われてしまうことが少なくありません。
感覚統合の力──未就学児だけのものではありません
未就学児向けの療育では、「感覚統合」が広く取り入れられています。これは、子どもが自分の身体や周囲の環境をうまく感じ取り、動かす力を育てる支援です。
感覚統合によって期待できる効果は多岐にわたります。
姿勢が安定する
体幹が強くなる
集中力が向上する
最後まで話を聞く力が育つ
これらは、まさに小学校生活で求められる力そのものです。にもかかわらず、小学生になると感覚統合の支援を受ける機会が激減してしまうのが現状です。
小学校の支援体制──通級・特別支援教室の課題
小学校では「情緒障害等通級指導教室」、東京都内では「特別支援教室」が、療育的な支援を担うべき場所だと思います。これらは無料で利用でき、保護者の送迎も不要という大きなメリットがあります。
しかし、実際には管理職の都合で配置された教員が担当することが多く、特別支援教育に詳しくないまま支援を行っているケースも見受けられます。中には「通常学級よりも楽そうだから」といった理由で教員自身が通級や特別支援教室を選ばれることもあります。
そのような管理職、教員都合を優先した教員配置が為された結果、感覚統合の重要性が理解されにくい環境が生まれています。
SST偏重の背景──感覚統合が敬遠される理由
通級や特別支援教室では、SST(ソーシャルスキルトレーニング)がよく取り入れられています。これは、教科指導に近く、指導者にとって扱いやすい教材です。理解しやすく、教えやすいという利点がある一方で、子ども一人ひとりの発達課題に深く向き合うことが難しくなる場合もあります。ある程度決まった教え方があり、指導案に起こしやすく、その通りにやればよいという考え方なので、個々の課題に寄り添わなくても理解しなくてもある程度のレベルの指導ができてしまうからです。
感覚統合は、発達の基本的な知識を身につけ、個々の特性を丁寧に分析する力が必要です。そのため、指導者側にとってはハードルが高く、敬遠されがちです。中には「感覚統合は不要」とまで言い切る先生もいるほどです。
その結果、教員自らが発達課題の基礎知識を学び、見取る力を鍛えなければならない感覚統合よりも、教員都合で指導しやすいSSTに支援が偏りやすくなってしまい、感覚統合が有効な児童への支援が届かないケースがあちこちの通級、特別支援教室で生まれています。
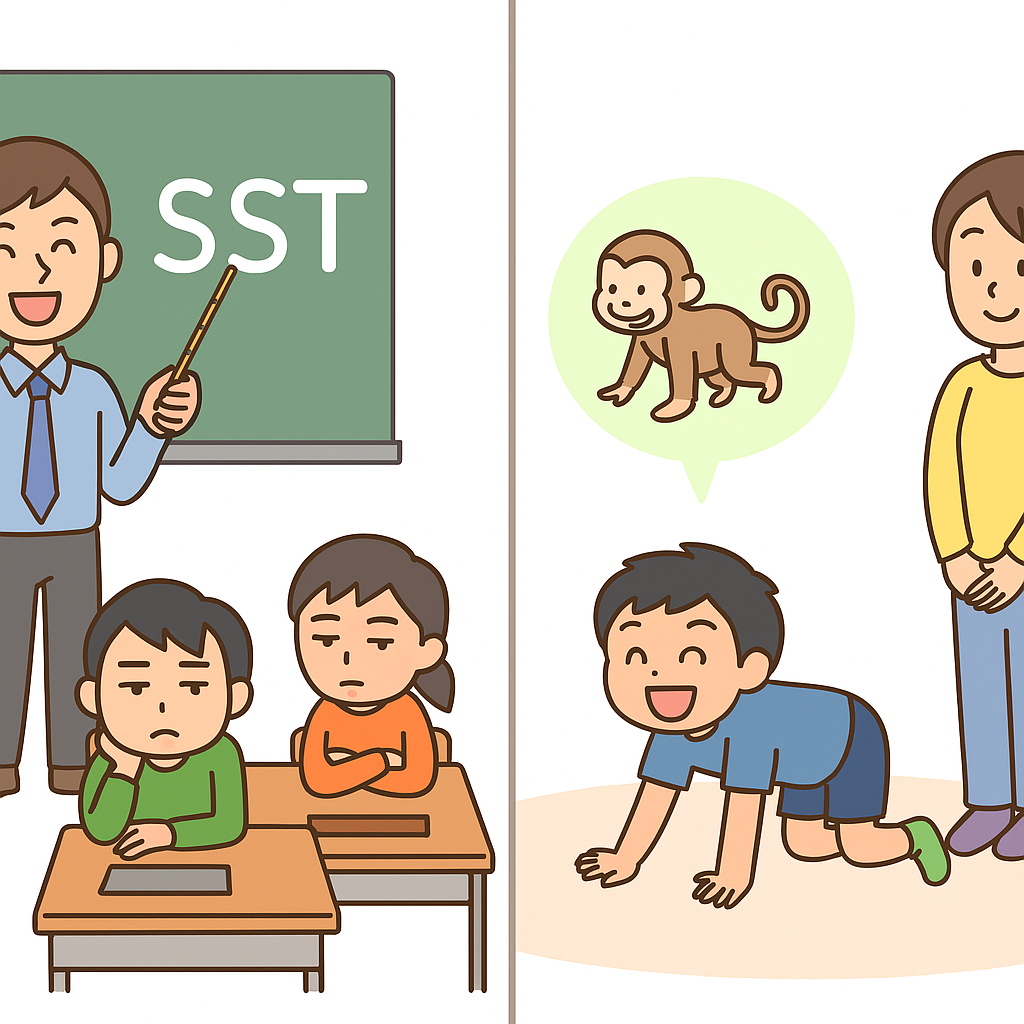
多摩湖畔通級支援室の取り組み──“塾感覚”で気軽に療育を
こうした現状を受け、多摩湖畔通級支援室では小学生が気軽に療育を受けられる場所を用意しました。公的機関では難しい支援も、気軽に塾を利用するような感覚で通える、柔軟な環境で提供しています。(ただし、WISC検査結果報告書の提出、あるいは受検を求めております)
土日祝日に実施するので、保護者の方も送迎がしやすく、近隣のお子さんが自転車で通室できるよう、駐輪場も用意しています。
「ちょっと気になる」「学校ではうまくいかないことがある」といった段階でも、安心してご相談いただけます。
生きやすさを育てるための練習を
当支援室の支援は、感覚統合や発達性協調運動障害(DCD)へのアプローチを中心に据えています。
集中力の向上
運動の苦手さの改善
自己肯定感の育成
これらを通じて、子どもたちが「生きやすさ」を身につけるための練習を、丁寧に、楽しく行っています。
「うちの子も気になるかも…」と思ったら、ぜひ一度、多摩湖畔通級支援室にご相談ください。お子さんの可能性を、一緒に見つけていきましょう。
小学生でも習い事感覚で療育的通級支援を受けられる「多摩湖畔通級支援室」をご利用ください。